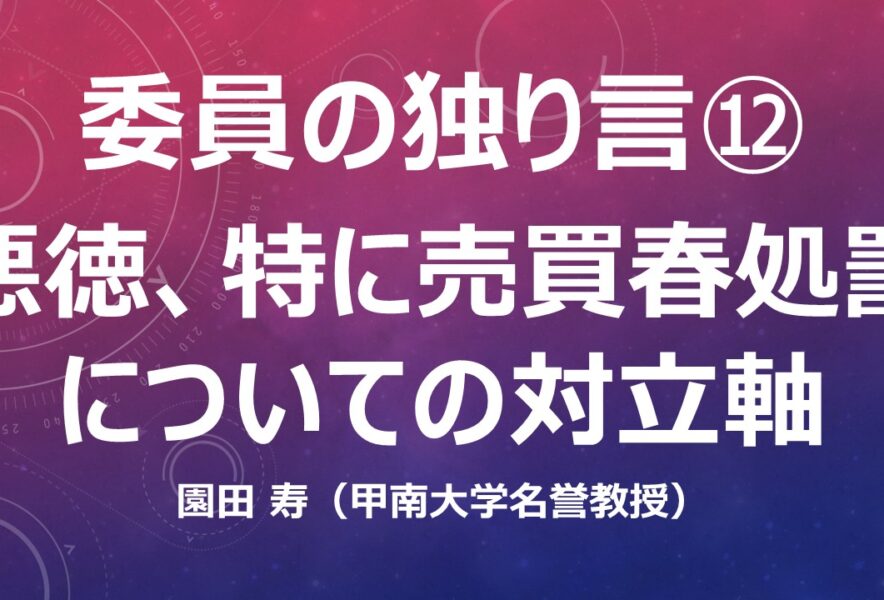園田 寿(甲南大学名誉教授)
「悪徳」とは、単なる個人の悪習慣ではなく、社会が何を許容し、何を制裁すべきかをめぐる規範的な境界線を可視化する概念である。一般に、飲酒、喫煙、薬物、賭博、性的逸脱といった行為が、歴史的に「悪徳」とされ、快楽的で反復的、かつ経済的に非生産的な行為群として、勤労の倫理や公的秩序との緊張関係を形成してきた。また、これらはしばしば裏社会と結びつき、支配的価値観に対抗する文化的領域を構成するものと理解されてきたのである。
こうした悪徳行為を国家が処罰・規制する根拠は、法的にはいくつかの原理に基づいている。
第一は、危害原則である。これは、他者や社会に重大な危害を与える行為のみを刑罰の対象とすべきだとする立場であり、売春や薬物使用は公衆衛生の悪化や組織犯罪の温床になるという理由で正当化されてきた。第二は、法的道徳主義であり、行為が本質的に不道徳であること自体を犯罪化の根拠とする。第三は、法的父権主義(法的パターナリズム)であり、本人の利益のために自由を制限することを容認し、依存や堕落からその人を守るという論理がとられる。しかしこれらの原理はいずれも、犯罪化がもたらす実際の社会的な帰結に対して十分に説得的ではない。
とくに売春や買春をめぐる規制が、その典型である。
歴史的に、処罰の焦点は売春行為そのものよりも、斡旋や売春宿経営といった周辺的な売春促進活動に向けられてきた(わが国の売春防止法もこのような基本構造をもっている)。そこには、女性を被害者として救済するという名目と、下層階級に対する道徳的な恐怖心も交錯していた。しかし、需要側である買春客の処罰は長らく曖昧であり、制度的にも真剣に議論されてこなかった。
近年、この点を正面から問い直したのが北欧モデルである。この立場は、売春を構造的搾取と捉え、供給側を非犯罪化する一方で、需要側である買春を犯罪化することで市場そのものを否定しようとする。つまり、買春は単なる私的行為ではなく、搾取構造を再生産する社会的加害行為と理解されるのである。他方で、これに対抗するのがハーム・リダクションや公衆衛生を重視する立場である。この視点からは、セックスワーカーの健康と安全こそを確保するべきであり、売春の刑罰化こそが巨大な闇市場を生み、暴力や性感染症の拡大を招いていると批判される。世界保健機関(WHO)も、2012年に「低・中所得国におけるセックスワーカーのためのHIVおよびその他の性感染症の予防と治療:公衆衛生アプローチのための勧告」(https://www.thenewhumanitarian.org/news/2012/12/18/new-who-guidelines-urge-decriminalization-sex-work?utm_source=chatgpt.com)を出している。
この対立の核心は、「何を主要な危害とみなすのか」という規範的選択にある。道徳的価値の崩壊や象徴的搾取を重視すれば、買春の犯罪化は論理的帰結となる。他方、現実に生じている暴力や疾病、社会的排除を最小化することを優先するなら、非犯罪化や合法化を前提とした公衆衛生的な規制が合理的選択となる。しかし議論にあたって重要なことは、刑法が単に危害を防ぐ技術的手段ではなく、犯罪とされた行為に対して、社会に特別な道徳的烙印(スティグマ)を押す仕組みであるという点である。悪徳を犯罪として扱い、処罰することは、他の経済的不正や契約違反には向けられない、特別な象徴的非難を伴うことを忘れてはならない。
要するに、買春を含む悪徳行為の処罰をめぐる議論は、個人の自律と自由を尊重する原則と、道徳的秩序を強権的に維持しようとする考え方とのあいだに横たわる緊張関係を映し出しているのである。国家は、国民に刑罰によって「徳」を教えるべきか、それとも「危害の管理」に徹するべきか。この問いそのものが、現代社会における刑法の役割を根底から問い返しているのである。(了)