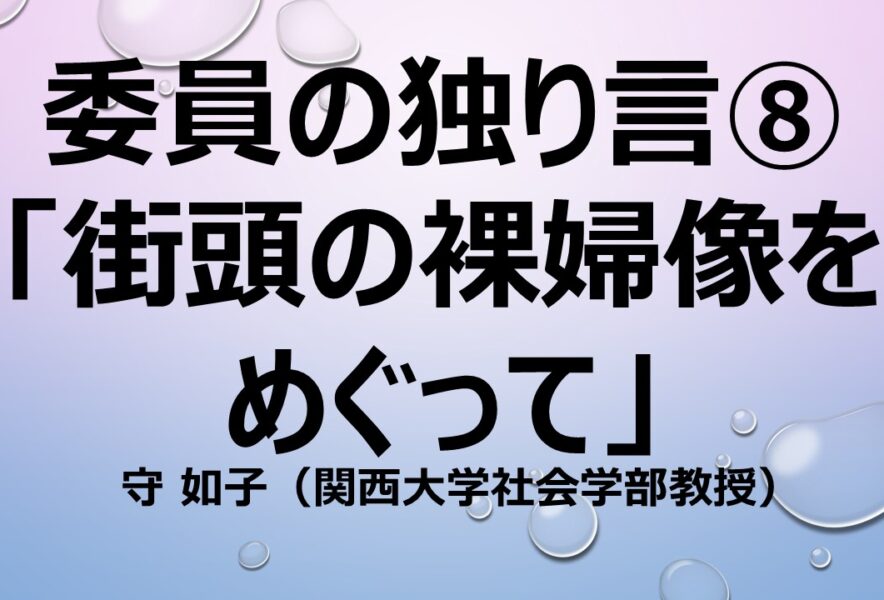守 如子(関西大学社会学部教授)
街の裸婦像の撤去が続いている問題について、実演者地位向上委員会の園田寿委員から「裸婦像撤去は文化の自滅行為」という指摘があった(2025年8月25日)。女性裸体像を猥褻(わいせつ)だときめつけ、不快感を理由に排除するのではなく、多様な表現が共存する社会を構築することこそが重要であるという指摘は最もだと考える。ただし、そもそも街の裸体像は(男性ではなく)女性であるのはなぜなのだろうかという疑問が残る。
私自身、街角におかれた裸婦像に疑問を抱いたことはなかった。初めてそのことに気づかされたのは、ある学生の卒業論文である。その学生、宝田真実さんは、その後修士論文で研究の成果をまとめている(「女性身体表象とジェンダー;公共空間の女性裸体像」奈良女子大学大学院2023年度修士論文)。ここではその内容からいくつかを紹介したい。
宝田さんは、1960年代から始まる「彫刻のあるまちづくり事業」を推進した自治体の中から、6都市の人物の彫刻204体を分析している。男性像、女性像、子ども像、家族像などさまざまな像のうち、最も多いものは女性像で、男性像の倍以上の数であった。また、男性像は名前がある人物で着衣の像が多いのに対し、女性像は無名の人物で裸体や半裸、透ける衣服の像が多いというジェンダーの偏向があることを明らかにしている。また、204体の彫刻の9割が男性作家によるものであったという。
歴史的にみると、戦前は、戦意向上や愛国心を扇動する武装した男性像が多くみられたが、それらは戦争と敗戦によって撤去された。それに代わって、無名の女性裸体像が平和や自由という観念の象徴として日本の公共空間に誕生していった。ただし、これらの像は「平和を女性としてイメージする男性の視線」を示しているのであって、「なんらかの女性が平和のために戦ったということは意味しない」(若桑みどり『イメージの歴史』筑摩書房、2012年)。時代が進む中で、平和という象徴性も、その土地との関連性や、設置の明確な理由もなくし、作家の習作のような裸体像が置かれるようになっていった。
これらの女性裸体像はそもそも市民アンケートなどによって設立されたものではなく、設立当初から批判的な声を上げる人々もいた。また、批判的な声を上げる人に対して、芸術のことをわかっていない「田舎者」などと批判する人もいた。
現在の一部地域の女性裸体像には胸や陰部に傷がつけられているものもあり、修復も撤去もできず、そのままの状態で放置されており、そのことに胸を痛めている市民がいることも宝田さんは描き出している。
私が宝田さんに指摘されるまで、街角の女性裸体像に違和感を抱くことはなかったのは、それほどに、女性裸体像に慣れきっていたからだろう。しかし、西洋社会においては、街角に女性の裸体像はほとんどないという(聖書のワンシーンを描く彫刻が墓地に置かれるなど、場面が限られているそうだ)。そのことも考え合わせてみると、無名の女性裸体像が乱立する日本の街角が不思議に思えてくる。
そもそも裸体をどのように捉えるかは、時代によって変化するものでもある。例えば、胸を例に出すと、かつての日本社会では女性の胸は必ずしもセクシュアルなものだとは捉えられていなかった(三橋順子『これからの時代を生き抜くためのジェンダー& セクシュアリティ論入門』辰巳出版、2023年)。私の子どもの頃にも、人前で授乳する女性が普通にいたことを覚えている。また、現代では、胸を出す水着を嫌がる男性もいるように、胸を出すことの意味合いも、時代とともに変わってきているのである。
猥褻(わいせつ)もまた、時代の中でその判断が変化してきた。西洋美術が入ってきたころには、裸体画が猥褻だとして、布がかけられたこともあったそうだ。だからこそ、当時の男性芸術家にとって、女性の裸体を表現することに意義があったのだろう。また、女神や聖人女性の裸体の表現はOKだが、娼婦の裸体の表現は猥褻だという議論もあったという。同じ女性の裸であるはずなのに、どうしてそんな線引きがなされるのだろうか。女性の裸体についての議論は、いつも表現される側の女性が置き去りにされているような気がしてならない。
社会が変わりゆく現在だからこそ、街角にある裸体像が女性のものだけであることについても、立ち止まって考えてみたい。女性の裸体像だけが芸術とされてきたことは、男性たちがこの社会で力を独占してきたことと関係しているのではないか。このような問いも踏まえたうえで、私たちは街角の女性の裸体彫刻にどう対峙していくのか、考えを深めていく必要があるだろう。
*本コラムを執筆するにあたり、多くのアドバイスをいただいた宝田真実さんに心より感謝申し上げます。