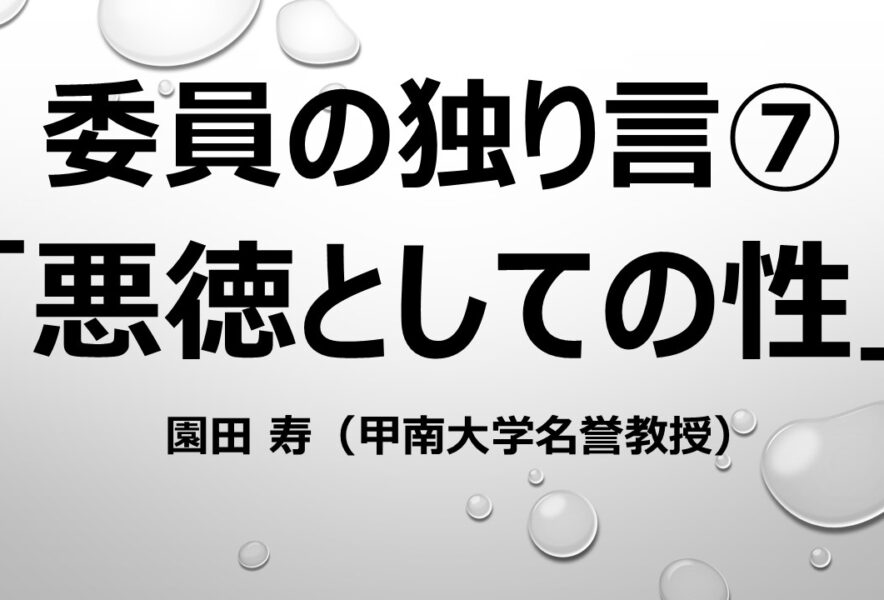園田寿(甲南大学名誉教授)
1.はじめに
売春や婚外性交渉、ポルノなどは、時には「悪徳」といわれ、時には「逸脱」として社会の性秩序を乱すと議論の対象になってきた。
しかし、それが「罪」として糾弾されるべきなのか、それとも「犯罪」として処罰されるべきなのか、あるいは「病」や「市場」という観点から統制されるべきなのかは、宗教的規範や刑事法、公衆衛生、そして経済的利害のいずれに重きを置くかによって左右されてきた。歴史的・文化的背景を切り離して、それを理解することはできない。
「悪徳」は、歴史的には 宗教や文化的規範、政治や経済と不可分の概念である。「悪徳」は人間の内面の問題であると同時に、社会秩序をどう設計するべきかという制度的選択の結果なのでもある。
2.宗教と性悪徳
まず、宗教的伝統においては、性をいかにコントロールするかは重要な問題だった。
儒教は礼によって性行動を秩序づけ、婚姻外での性交渉や淫行を不徳とみなした。仏教は性欲を煩悩の一つとし、抑制と克服に重きを置いた。キリスト教は原罪思想を背景に、性を人間の堕落の根源と位置づけ、性を婚姻の枠内に限定すべきだと説いた。イスラム教も姦通を厳罰化し、純潔を共同体維持のための根幹とみなした。
これらの伝統における「悪徳(vice)としての性」は、個人の救済や共同体の道徳秩序を脅かす「罪」としての意味合いが強かった。
3.産業革命と性悪徳
しかし19世紀に入り、産業革命と都市化が進展すると、「悪徳としての性」も大きく変わった。
匿名性の高い都市空間で売春は密かに、しかし公然と広がり、同時に梅毒などの性病がまん延した。
また大量の移民を背景に、アメリカやヨーロッパでは「白人奴隷」(white slavery)と呼ばれる人身売買が行われ、移民女性が性産業の犠牲となる姿が社会的危機として描かれた。
さらに、印刷機や写真の発達はポルノ市場を拡大させ、わいせつ表現を安価に流通させた。
こうした状況に対抗して「悪徳撲滅協会」(Society for the Suppression of Vice)などが、売春やポルノだけではなく、飲酒やギャンブル、無神論なども攻撃したが、拡大する市場の勢いに規制は腰砕けに終わった。つまりその頃はすでに、性の享楽はもはや一部階層の背徳的快楽(秘密事項)ではなく、大衆文化そのものの一部となっていたのである。
そしてこの変化は、国家にとって新たな課題を突きつけたのだった。
4.社会的法益と性悪徳
性病が社会に広がると、医師や公衆衛生の専門家などは、売春婦の登録検査制度の必要性、場合によっては隔離を求めたが、他方で、ヨーロッパでは性病の故意の伝播を犯罪行為だとして処罰の対象とした。これは日本でも同様であり、戦前にはすでに、性病を感染させた事例で傷害を認めた大審院の判決(明治41年2月25日)もある。
ここで「悪徳としての性」は、個人の罪や逸脱ではなく「共同体の健全さ(健康)を脅かすリスク」、つまり社会的法益に対する犯罪として定義し直され、警察権発動の根拠となったのである。
さらに軍事的理由も「悪徳としての性」の考え方を後押しした。
5.国家安全保障と性悪徳
日露戦争や第一次世界大戦では、(ロシアの敗北の原因となったといわれている)酒や売春が兵士を弱体化させるとの認識が広まり、性病撲滅キャンペーンが戦時の国策として推進された。兵士への酒の配給制度も中止され、性病の温床となっていた兵舎の近くにある売春宿も閉鎖された。「国家の強さは兵士の純潔と健康にかかっている」とされ、「悪徳としての性」は国家の安全保障上の問題へと転化していった。
ただし、「悪徳を正す改革」は必ずしも一枚岩ではなかった。
売春に関しては、衛生管理の観点から、禁止ではなく国による厳格な統制(管理)を支持する立場と、道徳的純潔を重視して全面廃止を求める立場とが鋭く対立した。
同様の分裂はアルコール問題でも見られ、規制か全面禁止かで意見が分かれた。宗教的にリベラルな改革者や世俗的改革者は規制を支持し、福音派プロテスタントは廃止を求めた(禁酒運動から禁酒法の制定へ)。
第二次世界大戦後、「悪徳としての性」に関する考え方は大きく変わった。戦時中における兵士と売春婦の接触は、もはや「罪」としてではなくもっぱら「感染予防」という衛生の観点から処理されるようになった。軍人に対しては「道徳的非難」よりも「予防措置の徹底」が強調され、性行為そのものを衛生面から管理する方針が主流となった。
その後、1980年代のエイズ流行期には一時的に「性的逸脱に対する懲罰的思想」が復活したものの、最終的には教育、予防、ハームリダクション(害の削減政策)へと議論が収斂していった。
またここで特筆すべきことは、「悪徳」という言葉自体が問題化したことである。すなわち、性を「悪徳」(vice)と呼ぶことは性病感染者やセックスワーカーにスティグマを与え、治療や社会的支援を妨げると考えられるようになったのである。
7.現代と性悪徳
現代において「悪徳としての性」はさらに複雑化している。
第一に、インターネットの拡大によってポルノや性サービスは国境を越えた巨大市場となり、ボーダーレス化は国際的な人身取引組織の活動を容易にした。
これにより、「悪徳としての性」は一国の道徳や衛生の問題にとどまらず、国際的な産業規制、人権問題、公衆衛生問題へと拡大しているのである。エイズ対策や世界保健機関による啓発キャンペーンはその象徴的な事例である。同時に、性産業の市場化・匿名化・国際化は規制を一層困難にし、従来の国家的規制モデルでは対応できない状況を生み出している。
第二に、しかし他方で、児童買春や児童ポルノに関しては、ほぼ普遍的に「絶対的禁止」が合意されている(ただし定義上の微妙な論争はある)。
1980年代に、(子どもはエイズにかからないという都市伝説を背景に)東南アジアへの児童買春ツアーが世界的な問題になったが、それは 「個人の自由な選択」では決して正当化できない領域の問題であり、人間の尊厳を根本から破壊して、市場的搾取を通じて社会秩序を腐食させる「絶対的悪」であるという認識が高まった。児童への性的搾取は、「同意に基づく性行為」という枠組みから完全に外れてしまい、単なる「背徳的快楽」の域を超えているからである。それゆえこれは、悪徳の中でも「邪悪なるもの」と別次元で捉えられている。
8.まとめ―新自由主義経済と性悪徳―
最後に、以上の歴史的展開を総合すると、「悪徳としての性」は固定的な概念ではなく、さまざまな社会的文脈に応じて絶えず再構築されてきたことが分かる。
宗教的には「罪」とされ、近代国家においては「犯罪問題」や「衛生リスク」とされ、現代においては「市場と規制の対象」として再定義されている。19世紀末から20世紀初頭には進歩的改革運動がその不当性を強調したが、現代の新自由主義的市場経済のもとでは性の享楽がむしろ消費文化の一部として経済的に制度化されている。
すなわち、「悪徳としての性」は「人間の普遍的堕落」ではなく、歴史的な制約を受けたカテゴリーであり、その射程は道徳、国家安全保障、産業問題といった複数の要因によって規定されるのである。今やグローバル資本主義の下で再編される性産業を、どのような観点から捉え直すかが問題となっているのである。(了)