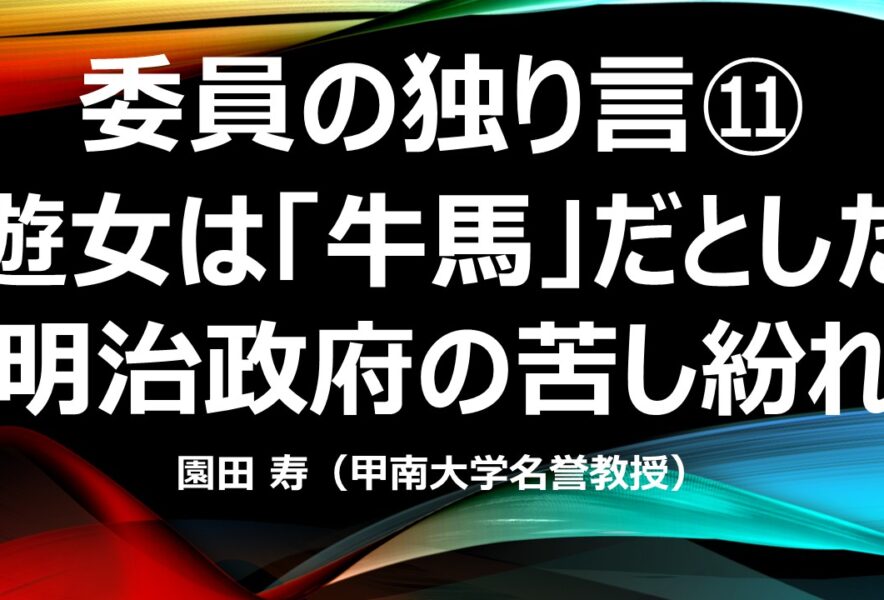園田 寿(甲南大学名誉教授)
明治5(1872)年、真夏の熱気が籠もる横浜港に、修理のために一隻の帆船が滑り込んだ。ペルー船籍、マリア・ルス号である。その船底には、マカオからペルーの銀山へと売り飛ばされる清国人苦力(クーリー)231名が動物同然の扱いで詰め込まれていた。
ある夜、数人の苦力が救助を求めて暗い海へと身を投げた。男らはイギリス軍艦に救い上げられ、震える声で船内の惨状を訴えた。この命がけの告発が、生まれたばかりの明治政府を揺るがす大事件になったのである。イギリスは直ちに日本に救助の要請をした。
時の外務卿・副島種臣は、この訴えを聞くや否や、神奈川県権令(今の県知事)の大江卓に捜査を命じた。大江は法律顧問の米国人ジョージ・ヒルと共に、マリア・ルス号へ足を踏み入れた。異臭漂う薄暗い船底で彼が目にしたのは、人としての尊厳を剥ぎ取られ、家畜のような状況に置かれた人びとの悲惨な姿であった。苦力たちを解放すべく、大江は横浜に特設裁判所を設けた。
しかし、船長側の弁護に立ったイギリス人弁護士ディキンズの放った言葉は、明治政府の急所を突き刺した。
「自国内で『遊廓』という名の女奴隷を公認している国が、どの口で人道を説くのか」
この一言は、不平等条約を矯正しようと懸命になっていた政府にとって、反論できない矛盾であった。裁判の結果、マリア・ルス号の苦力は解放されて清国に戻されたが、政府内では、「遊郭」を廃止して売娼地域の特定性を解除しようとする司法省(黙認政策)と、社会の安寧を優先して売娼を特定地域に囲い込もうとする大蔵省との間で激論が交わされた。政府は結局国際社会の前に女たちを絡めていた鎖を断たざるをえなかった。
これが、明治5年10月2日太政官布告第295号、世に言う「芸娼妓解放令」である。
しかし、問題は彼女たちが抱えていた多額の借金である。
その布告に添えられた司法省の達しには、驚くべき言葉が添えられていた。
「娼妓や芸妓は、人身の権利を失った者であり、牛馬と選ぶところがない。ゆえに、牛馬に貸した金の返済を求める道理はない」
女たちは牛馬と同じであるから、前借金という足枷を外して野に放つべし、というのである。政府にとっても突然の解放令に、吉原の大門を出た女たちの生活を保障する公的な手立てを講ずる余裕はなかった。結果的に解放令は、文明国としての体裁を保つための冷徹なレトリックになったのである。
そして解放令からわずか一年後に政府は、「貸座敷渡世規則」を公布する 。これによって遊廓は「場所を貸す楼主」と「自らの意志で性稼業に就く娼妓」との間の「自由契約」となった 。前借金は形を変えて存続し、女たちは再び「公娼」という枠組みの中へ囲い込まれていった 。大蔵省の路線が勝利した結果になったのである。
さらに政府は、「性病予防」という公衆衛生の枠組みを構築した 。これにより、遊廓は単なる色街から、国家が強制的な検診と監視を行う「衛生管理の場」へと変貌を遂げたのである 。
文明開化という大きな波の中で、女たちは「公衆衛生」と「風俗警察」という国家の管理下に組み込まれていった。大江卓がマリア・ルス号裁判で示した人道の理想は、こうして現代へと続く「性の管理」という名の複雑な仕組みへと塗り替えられていったのである。(了)
【参考文献】
今西一「芸娼妓『解放令』に関する一考察」商学研究57巻4号(2007年)
大野聖良「日本における『人身取引』の問題化―『人身取引』概念の変遷を手がかりに―」(2017年)