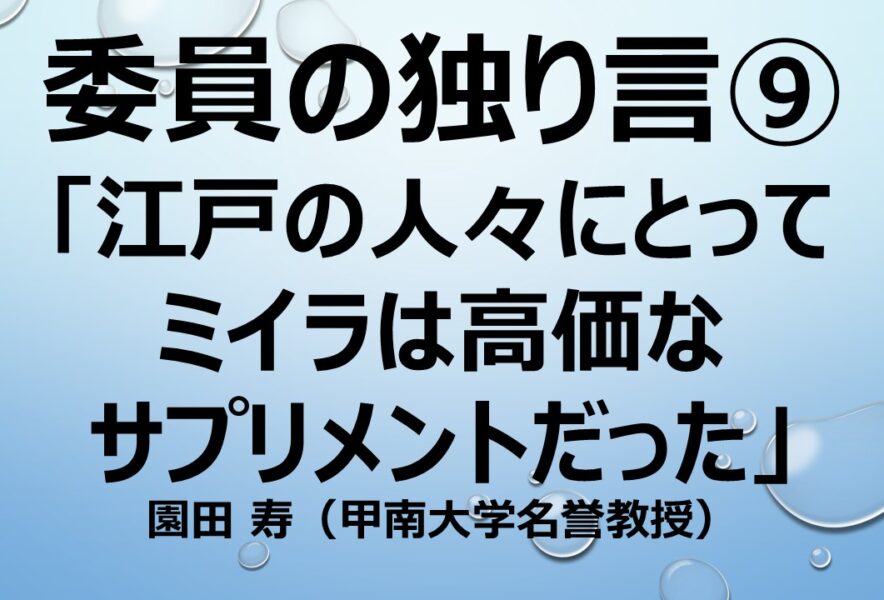園田 寿(甲南大学名誉教授)
江戸時代、遠くエジプトの砂漠から運ばれた「木乃伊(ミイラ)」は、朝鮮人参や底野迦(テリアカ、阿片を含む解毒剤)と並んで、オランダ船がもたらす最高級の霊薬として珍重されていた。
粉砕したミイラを万能薬として摂取するこの奇怪な習慣は、実は日本独自のものではなく11世紀以降のヨーロッパで定着していたものである。これが長崎の出島を通じて日本に流入した。かつてフランソワⅠ世も常備したとされるこの薬は、打撲やペストにさえ効くと信じられており、鎖国の扉の向こうで、日本人はその世界的流行に敏感に反応していたのである。
蘭学の巨匠、大槻玄沢(1757-1827)は、『六物新志』(1786年)において、ミイラを「遠い過去に防腐処置を施された高貴な人びとの遺体」と説明し、千年以上も腐敗しなかったその驚異的な保存力こそが、生きた人間の身体を固め、骨折治療や喀血止めに効くのであると書いている。
これは、死してなお朽ちない永遠性が生者を救うという、呪術的とも言える素朴な医学理論である。
さらに言えば、すでに日本には死体を薬として求める習慣が存在していたのである。
幕府の首斬り役人を務めた山田浅右衛門は、代々副業として斬首した罪人の遺体から肝臓や胆嚢を取り出し、「人胆丸(じんたんがん)」や「浅右衛門丸」と称する丸薬を製造・販売していた。これもまた、当時不治の病と恐れられた労咳(結核)の特効薬と信じられていた。海を渡ってきたミイラであれ、刑場の露と消えた極悪人であれ、そこには人間の生命力が凝縮された部位を体内に取り込むことで不治の病に対抗するという切なる願望が共通して流れていたのである。
しかし、高値で取引される市場にはつねに贋作の問題が広がる。17世紀の末には京都で「新着ミイラ」と呼ばれる偽物が横行していたとの記録がある。その正体は乾燥させた馬の肉である。ミイラの需要に乗じて、商人たちは燻製にした馬肉を売りさばいていたのだ。玄沢は、「藍黒色で軽く、肉付きの良いものが良い」と、偽物との違いを強調して警告している。
当時の日本は、おそらく意外なほど外に開かれていたのだろう。鎖国下にありながら、人びとはオランダ船という細い糸を通じて、欧州の「知」と「習慣」を貪欲に取り込んでいた。今では博物館に眠るミイラだが、かつてその一部は薬研(やげん)ですり潰され、富裕な江戸の人びとの血肉となり、慰めとなっていた。そこには、健康と長寿のためならばという、貪欲で力強い生のエネルギーも見られるのである。
翻って我々もまた、科学的根拠が定かでない健康食品や薬、「万能」を謳う新技術に飛びつき、救いを求めてはいないか。根底にある不安と渇望の構造は、江戸の人びととそれほど変わっていないのかもしれない。 (了)
【参考資料】
・Jonas Ruegg, “Early Modern Japan and the Problem of ‘Drugs,’” in Drugs and the Politics of Consumption in Japan, edited by Judith Vitale, Oleg Benesch, and Miriam Kingberg Kadia (Leiden/Boston: Brill, 2023)
・氏家幹人『江戸の怪奇譚』(講談社、2005年)
・フレデリック ・クレインス「江戸時代のミイラ熱」(国際日本文化研究センター「日本関係欧文史料の世界」エッセイ、2022年)