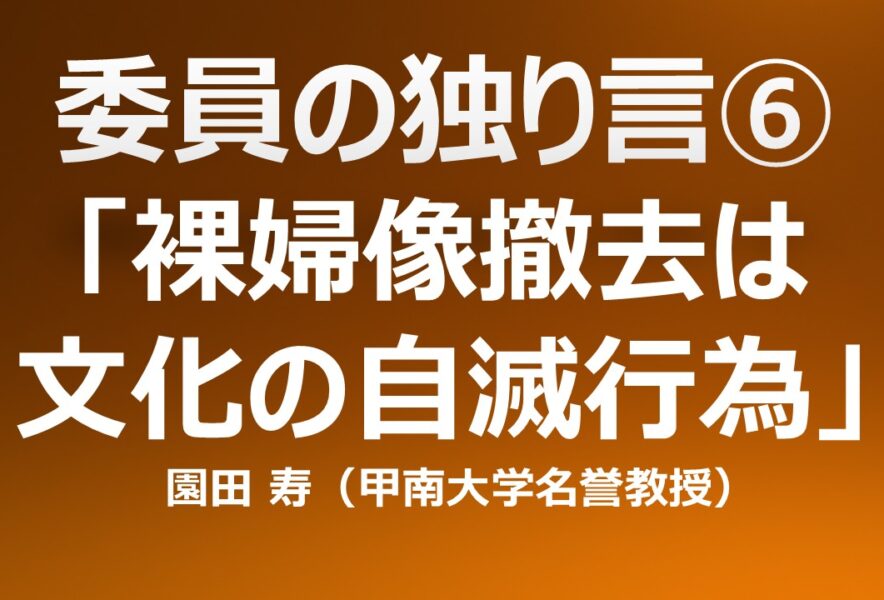園田寿(甲南大学名誉教授)
1.はじめに
日本の公共空間に設置された「裸婦像」を撤去すべきだ、とする声が一部で強くなっている。その理由としては、「子どもの目に触れる」、「公共の場にふさわしくない」、「公序良俗に反する」、「わいせつに当たる」などが挙げられる。しかしこれらの主張は、法的にはもちろん、文化的にも正当化されるものではない。とりわけ「わいせつ」や「性的不快感」と芸術表現とを安易に結びつける議論は、文化史的にも問題が大きい。
そもそも、わいせつという概念は歴史的・社会的に形成されてきたものであり、時代や社会状況によって判断基準が大きく変動してきた。そのため、芸術表現としての裸婦像を「わいせつ」と同列に扱い、撤去するという動きは、わいせつ規制の歴史的文脈を無視するのみならず、芸術表現の公共的価値を矮小化する危険を孕むものである。
本稿では、公共空間における性表現の意義を検討することを通じて、裸婦像撤去の動きを批判的に分析したいと思う。
2.わいせつの概念と裸婦像の不当な接合
刑法第175条は、わいせつ文書・図画等の陳列等を処罰対象としているが、その「わいせつ」とは何かという点については判例上の定義に依拠している。最高裁は1951年の「サンデー娯楽事件」で初めていわゆる「わいせつ3要件」を示し、以後の判例もこれを踏襲してきた。すなわち、(1)いたずらに性欲を興奮・刺激させ、(2)普通人の性的羞恥心を害し、かつ(3)善良な性的道義観念に反すること、という三点である。また、芸術性によってわいせつ性が薄まることも、裁判所は認めている。
しかし、町中に設置される裸婦像は、もちろん性欲を刺激することを意図したものではなく、むしろ人体美の造形や生命の象徴といった芸術的文脈に位置づけられるものである。
たとえばルネサンス期以降の西洋美術において、裸体像は「人間の理想美」を表現する中心的な主題であり、日本においても近代彫刻の潮流の中で裸体像は教育・文化施設や公共施設、公園などに数多く設置されてきた。
これらを「わいせつ」あるいは「性的に不快」とみなし撤去しようとすることは、刑法上のわいせつ概念と芸術的裸体表現とを混同するものであり、法的妥当性を欠いている。裸婦像が芸術作品として公共空間に存在してきた以上、わいせつ性や性的な不快感を理由に撤去することは、司法判断の蓄積を無視した恣意的な措置なのである。
3.公共空間と〈仮想的嫌悪感〉
そもそも、わいせつの概念は時代によって大きく変動する流動的なものである。かつて発禁処分となった『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』は、今日では普通に流通しており、通販でも簡単に入手できる。これは、かつて「犯罪」とされた表現が、時代の変化とともに芸術的価値を再評価され得ることを示している。
裸婦像もまた、現在の一時的な「不快感」を理由に撤去してしまえば、将来の世代が文化を享受し、多様な美意識を形成する機会を奪うことになる。撤去は単なるモラル判断ではなく、社会全体が自らの文化資産を切り捨てる「文化的自滅行為」といわざるを得ない。
刑法175条におけるわいせつ罪は、「実際に見た人が不快感だと思った」ことが要件ではない。つまり、個人の直接的な感情的被害を保護するものではない。裁判所は「性的表現が公共空間に存在すること自体が不快である」と感じる人びとの〈仮想的な嫌悪感〉を保護するのである。
この独特の理論構造は、確かに戦後社会において性秩序を守る役割を果たしてきたが、インターネット時代においては妥当性を失いつつある。今日では、性的コンテンツにアクセスするか否かは個人が自由に選択可能であり、「存在していること自体が不快」という論理は説得力を欠いているのである。
裸婦像撤去要求もまた、この〈仮想的嫌悪感〉の論理に依拠している。しかし、公共空間における芸術表現は、まさに多様な価値観が共存することを象徴する場であり、一部の市民の「不快感」を根拠に排除することは、公共性の本質を矮小化する危険がある。公共空間は「万人にとって完全に無害で快適な空間」である必要はなく、多様な表現が共存し、時に摩擦を生み出す場であることに意義があるのである。
4.おわりに
裸婦像をめぐる論争は、単に「好ましいか否か」という趣味・感情の問題ではなく、法・文化・社会の根幹に関わる問題である。わいせつと芸術の境界を再考し、裸婦像撤去要求の妥当性こそを議論すべきである。
そもそも芸術は、つねに社会の支配的な価値観、常識に挑戦し、時に摩擦を生み出す。しかし、それこそが公共空間における芸術の意義である。不快感を理由に排除するのではなく、多様な表現が共存する社会を構築することこそが重要であると思われるのである。(了)