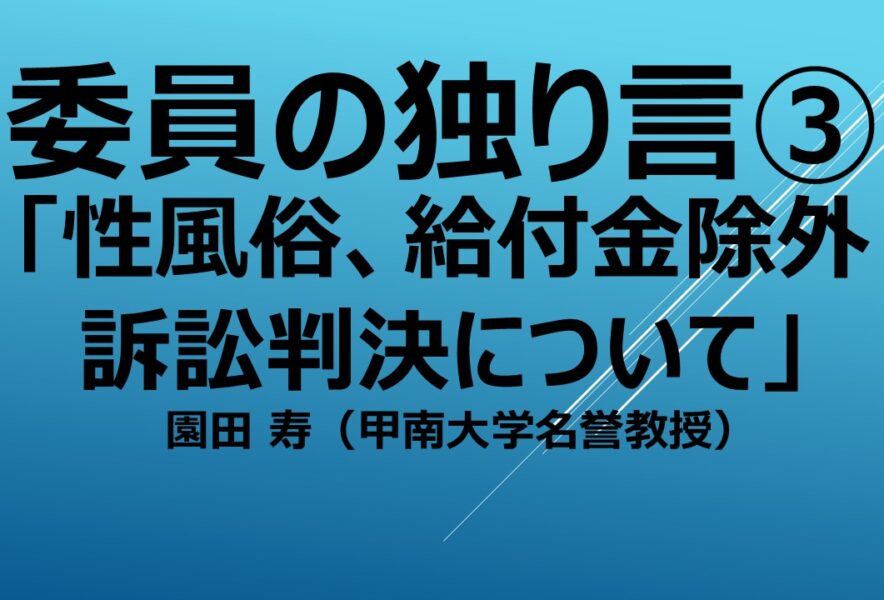園田寿(甲南大学名誉教授)
<はじめに>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を支援する給付金が、無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリヘル)を行う事業者には支給されなかった。
事業者は、この給付対象からの除外が憲法第14条第1項(法の下の平等)と第22条第1項(職業選択の自由)に違反すると主張したが、最高裁は次のように判断して、この訴えを退けた。
当該営業の事業内容とその法的位置付け(風俗営業法による規制の対象であり、その健全化が観念できないとされている点)に鑑み、公費を投じて事業継続を支援することが相当でないと判断した国側の措置は不合理ではない(最高裁(1小)令和7年6月16日判決)。
ただし一人の裁判官が、給付金の緊急性と目的、そして当該営業が法的に禁止されていない点を重視して、除外は憲法に違反するという反対意見を述べた。
最高裁は、国の給付金政策が個人の自由、道徳、司法の役割にどのように関わるべきかという点で重要な判断を行っている。以下では、いくつかの視点から、この判決について考えてみたい。
<道徳的判断に基づく公的支援政策をどう考えるべきか(法道徳主義の問題)>
本来、公的支援政策、とくに緊急性を有するものは、困窮する国民すべてに実施されるべきものである。その際に、「不道徳な行為」であることを理由に、それを制限することが許されるのだろうか。これが、本件訴訟が投げかけた問題である。
世の中に不道徳な行為は無数にあるが、不道徳を根拠に、生存そのものが脅かされてはならない。そもそも公的支援政策は、国民が生きることそのものに関係することであり、国民が「沈むことのないようなネット」を張ることを意味する。「大多数の国民が共有する性的道義観念に反する」という理由で、このネットを制限することは許されない。
仮に百歩譲って本件性風俗業が「道義観念」に反するとみなされても、それが公的支援からの排除を正当化する理由にはならない。反対意見は、給付金の主旨との整合性から「(制限に)合理的な根拠は見当たらない」と憲法違反を断じているが、これはまさに法道徳主義への批判である。
<排除の正当化根拠(温情的干渉への批判)>
行為そのものが明確な危害や権利侵害を伴わない限り、公的支援の制限という「制裁」を正当化することは困難である。
社会でもっとも厳しい制裁を予定している刑法では、「やむを得ない正当な理由がない限り、誰も罰せられるべきではない」という原則が妥当している。性風俗業の給付金除外はもちろん刑罰ではないが、事実上の「制裁」と変わらない。
多数意見は、本件営業はデリヘル嬢が接客の過程で客から「尊厳を害されるおそれ」のある事業なので、デリヘル嬢を守るためにも他の業種と同じような保護を与えることは適切ではないとしたのに対し、反対意見は、デリヘルが法律で禁止されている「売春」とは異なり合法な職業活動であり、自らの意思で従事する者の尊厳を当然に害するとは断言できないと反論している。
そもそも国家が個人の尊厳を守るために、合法とされている職業活動を制限することが正当化されるのか。これは、「道徳的に不適切な職業」に従事する労働者自身の「尊厳」を守るためというパターナリズム的な考え方(温情的干渉)に基づくものである。法秩序が合法としている以外に、反対意見が本人の自らの意思を重視している点も、このパターナリズムへの反論と読み取れる。
<「間違ったメッセージを送る」という懸念>
おそらく多数意見の根底には、一律に給付することで、国民に性風俗業を正面から認知することになるとの不適切なメッセージを送ることになる、との懸念があると思われる。しかし、これは不当な政策を維持する理由にはならない。給付金支給は、単に合法な事業を支援する行為であり、その行為の道徳的承認を意味するものではないからである。
<結論>
以上より多数意見が述べる性風俗業に対する給付金除外は、道徳的判断を安易に基礎に置く福祉的政策の不当性、パターナリズム、そして法の下の平等原則に対する不徹底といった問題を抱えていると評することができる。(了)